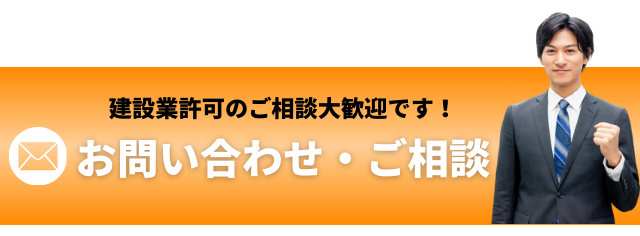建設業許可を取得したらそれで終わりというわけではありません。
建設業許可には5年間という有効期限があり、5年間の期間を過ぎる前に
「更新」の手続きをしなければなりません。
そこでこの記事では建設業許可の更新に必要な手続きや条件をわかりやすく解説していきます。
はじめに
建設業許可は取得の申請をするのに膨大な資料の用意が必要です。
実は更新許可でも同じくらいの量の書類が必要だとご存知でしょうか?
建設業許可更新の時には建設業許可を新規申請するときと同じくらい書類が必要というのはある理由があるのです。
実は建設業許可は国や県から「厳格な要件をクリアした建設業者」としてお墨付きをもらう制度です。更新許可は5年間ごとに受ける必要がありますが、新規に許可を取得したり、前回の更新から5年も経過すると、会社によってはいろいろと変化が起きているはずです。
県や国から「厳格な要件を変わらずクリアしているか」という審査を受けるために、5年間の更新許可は新規許可と同じくらいの量の書類が必要なのです。
従業員の増減がないか
建設業許可は5年の更新が必要とお伝えしましたが、
5年間という期間が過ぎれば、たとえば会社の従業員の面々は
増えた方もいれば、いなくなった方もいる会社が多いと思います。
実は建設業許可には技術者という工事の管理をするのに必要な人員がその会社に在籍しているか、
がとても重要な条件になってきます。
たとえば建設業許可申請に必須の「経営業務の管理責任者」や「営業所の専任技術者」が退職しており、
後任の従業員がいない!となると、建設業許可の更新はまず難しいでしょう。
新規許可申請の時に技術者や責任者の要件を満たしたからOKというわけではなく、
5年の更新ごとにもそのような要件をクリアしていなければ、更新許可が下りることはありません。
会社住所や代表者に変更がないか
5年間の間に会社を移転したり、代表者が変わっていると、変更があってから一定の期間以内に
変更届を提出しなければなりません。
変更届で変更が済んでいれば問題ありませんが、変更を忘れていた!
という方は、更新の手続きよりも先に変更届が必要です。
保険関係に変更はないか
従業員を雇用して建設業を営んでおられる法人の多くが、健康保険や厚生年金に加入しているでしょう。
ですが新規の許可申請の時と加入している保険に変わりはないか、
別の健康保険に変更していないか、その内容もチェックされます。
きちんと納税をしているのか、税金の未納・滞納がないか
建設業許可は国や県からお墨付きをもらう制度です。
一企業として税金の未納や滞納がある場合は、企業の信頼性のイメージダウンにもつながります。
また、未納がある場合には更新許可を受けることは100%不可能です。
更新許可を受ける前に必ず、
払い忘れていた税金がないか、確認しておきましょう。
成年被後見人や被保佐人に該当しないか
成年被後見人とは、「精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にあるもの」といって、
わかりやすく一例をあげると重度の認知症などにかかっており、
能力が回復することはあっても大抵の場合、判断能力がほとんどない状態、
被保佐人とは、「事理弁識能力が不十分なこと」とあり、軽い認知症など、精神上の障がいにより、
支援を受けなければ契約等の意味・内容を自ら判断できない状態にあることを言います。
いずれも家庭裁判所の審判が下りると、そのことが登記されますが、
そのどちらにも該当しないことを証明する書類です。
破産手続きを受けていないか
破産手続きを受けていると必ずしも更新許可を受けられないわけではなく、
破産手続きを受けていて「復権」を得ないまでの間(おおよそ10年と言われています)は建設業許可の更新を受けることが不可能です。
まとめ
他にも条件はありますが大きな要件をピックアップして説明させていただきました。
該当することはなかったでしょうか?
変更届を出せばよい内容であればすぐに変更届で届出を済ませれば問題ありませんが、
それ以外の破産手続きを受けたことがある場合や、経営業務の管理責任者が不在の場合はただちに更新許可に影響があるといえます。
当事務所では建設業許可の新規許可申請をはじめ、更新許可、変更届、事業年度終了届など
建設業許可にかかわる申請を承っています。
更新許可で失敗したくない。
主任技術者や専任技術者が退職しそう(退職した)など。
建設業許可に関するご相談はお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ・ご相談はこちら
9005-1137
営業時間 9:30~17:30(土日祝休み)